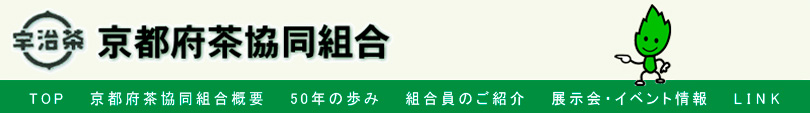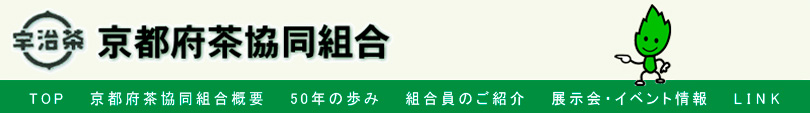明恵上人(みょうえじょうにん)から栄西禅師(えいさいぜんし)に伝承され、京都栂尾(とがのお)に植え、そこからできた茶を「本茶」とし、その他の産地茶を「非茶」と言い、これの飲み分けが普及しましたが、これにかける賞品も大変豪華なもので、それが時によっては、賭け事にまで発展し、人間関係の破たんにつながり、やがて足利幕府(室町時代)は禁止令を交付するまでに至ったそうです。
今日の茶かぶきでは、玉露や煎茶を主として用い、いろいろなところで行われています。初心者の方には、娯楽や趣味に加え、お茶を通じて人間関係の交流の場として、また専門的には、お茶の鑑定眼を養い、製造の良否の判別、優良茶生産の向上に役立っています。
競技内容としては、一般的に五種五煎法で各産地別で同一金額のお茶を5種類飲み、これを5回繰り返して行い、5回の合計点数を競います。
なかなかこれが難しく、専門の方でも満点をとるのは、容易なことではないようです。
人間には、五感(視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚)が備わっていますが、生活が便利になるとともに、五感も鈍くなってきているといわれています。
茶かぶきでは、五感、特に視覚、臭覚、味覚ときには、『第六感』も使って、足利時代に貴族の遊びとして広がった「茶香服」をお楽しみください。 |