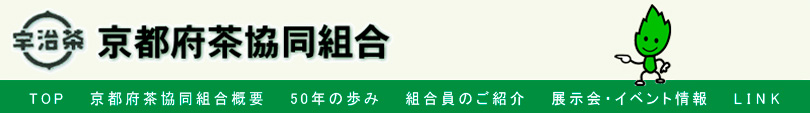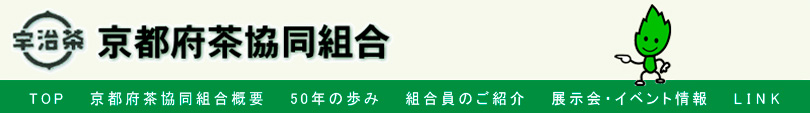お茶壺道中という将軍家の行列、しかも摂家、宮門跡に次ぐ高い位を授かっての権威に、大名たちは道中で行き会うことがあれば、道をあけて先に通すことになっていました。
「下にぃ、下にぃ」と通る行列に民衆は土下座し、少しでも粗略な態度を見せると、容赦なく罰せられたそうです。また、行列に人馬を提供するものは、農繁期に重なり、本業を投げ打って使役に従事しなければならず、その苦痛は並大抵ではなかったと想像できます。
♪ズイズイズッコロバシ胡麻味噌ズイ 茶壺に追われて
戸をピッシャン 抜けたーら ドンドコショ〜〜♪
の童謡からも、当時の民衆の道中に対する畏怖が伝わってきます。こうしたことから、お茶壺道中は、沿道の民衆にとって非常に迷惑であり、恐れられていたと考えられます。
豪華であったお茶壺道中も、八代将軍、吉宗の行った享保の改革による倹約令の一つとして簡素化され、江戸から宇治に運び出す茶壺は三個に限定され、幕府も経費削減を図りました。
こうして、毎年休みなく235回続いたお茶壺道中も、慶応3年(1867年)江戸幕府の終焉によって、その役目を終えることとなります。
しかし、お茶壺道中が終わってからも、宇治茶の名声が衰えることはありませんでした。
それは、宇治茶師が将軍家御用のお茶作りのため、日々研鑚に努め、創意と工夫を重ねて宇治独特の製法を編みだし、良質茶の生産に励んだため、すでに、日本の津々浦々にまで宇治茶の名声が知れ渡っていたからです。今日における宇治茶の発展は、将軍家抜きでは語れないものとなったのです。 |